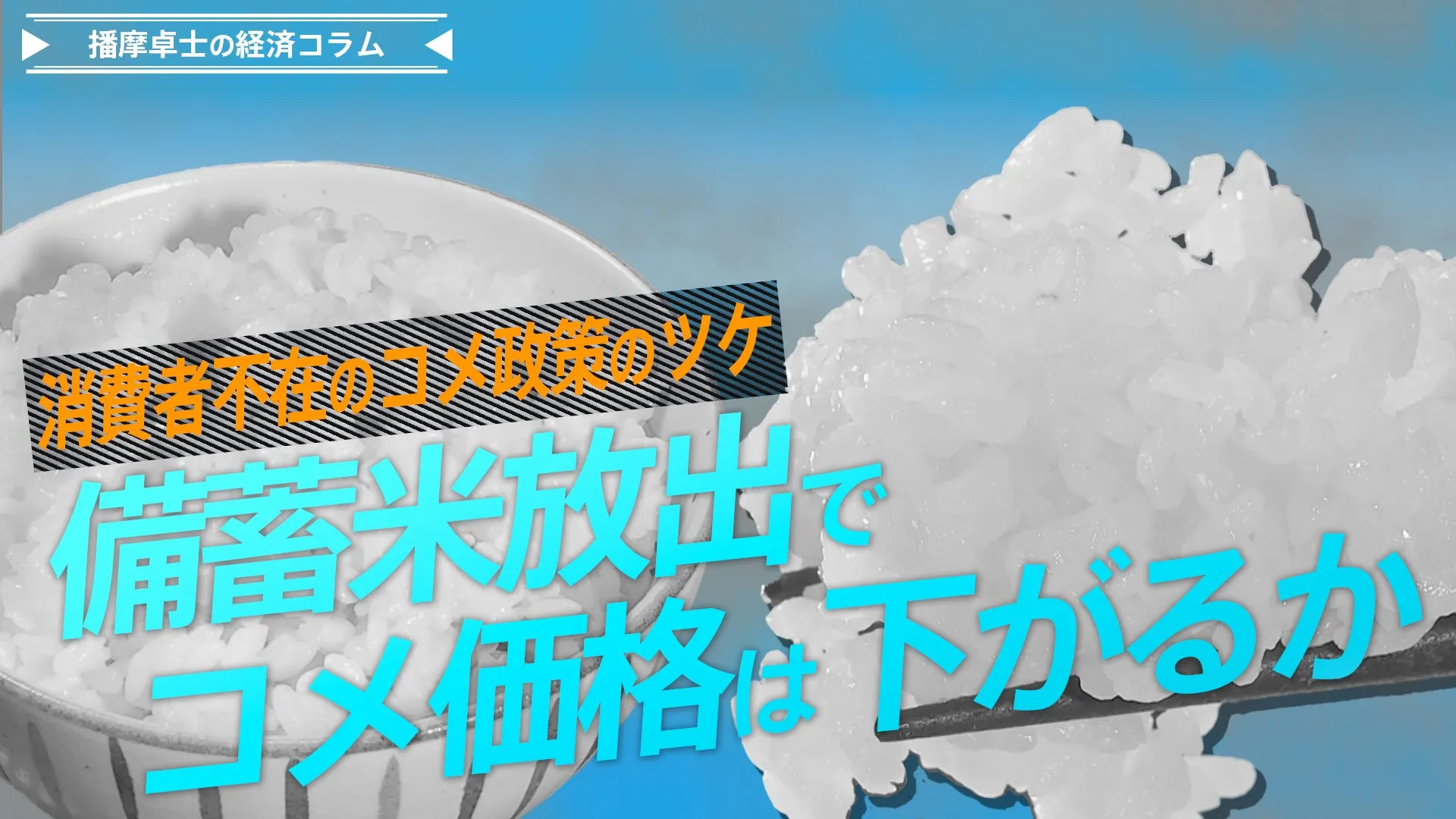
全くひどい話です。政府がようやく備蓄米の放出を決めました。コメ不足が叫ばれ始めたのは去年7月のこと。この間、農水省は「新米が出回れば価格は落ち着く」などと、根拠なき無策を続けました。世論の求めに応じて、もっと早く放出を検討していたら、これほど価格は高騰せず、出す量も少なく済んだはずです。
【写真を見る】備蓄米放出でコメ価格は下がるか、消費者不在のコメ政策のツケ【播摩卓士の経済コラム】
コメ価格は過去最高更新
21日に発表された1月の全国消費者物価によれば、コメ類の価格は前年同月比で、70.9%も上昇し、比較可能な1971年以来最大の上げ幅を更新しました。生鮮食品を除く消費者物価は3.2%もの高い上昇が続いていますが、コメだけで0.2ポイント程度、押し上げた計算で、エネルギーに次ぐインフレ要因になっています。
店頭を見てみると、あきたこまちなどのブランド米は、5キロ4000円超が当たり前で、1年前の2倍が普通です。大凶作や戦争でもないのに、主食の価格が倍になるという信じ難い事態が続いているのです。コメ売り場の棚も変わらず、スカスカという状況です。
さすがに総理官邸からも強い圧力がかかって、無策を決め込んでいた農水省も重い腰を上げ、14日、政府備蓄米21万トンの放出をようやく決めたのでした。
21万トン放出でも価格低下は不透明
放出する政府備蓄米は21万トンとしており、第一弾として15万トンを出す計画です。農水省によると、JA全農など大手の集荷業者が農家から買い集めた24年産のコメが、12月時点で、前年比20.6万トンも少なくなっています。それに見合う量を放出すれば、「滞っている流通」を正常化できるとしています。
21万トンという放出量は、政府備蓄米の2割ですし、1年のコメ生産量が600万トン余りという点から見ても、決して小さくない量です。しかし、これだけ高騰した価格の低下にどれだけつながるかは、不透明です。
確かに、放出された備蓄米が店頭に並べば、そのコメ自体や直接競合するコメの価格は安くはなるでしょうが、そうでない銘柄米の価格低下は限定的でしょう。また、卸も小売りも、これまで高い価格でコメを仕入れているので、それを大きく下回る価格で販売することには躊躇するでしょう。専門家の間では、平均で1~2割程度の値下がりに留まるのではないかとの見方が強く、消費者が期待している「できるだけ去年に近い値段」には、程遠いとみられます。
21万トンはどこに消えたのか
農水省は、滞っているのは、あくまで「流通」とみています。24年産のコメの生産量は、前年より3%多い679万トンだったので、「コメは足りている」としています。生産が増えたにもかかわらず、流通量が減っているのは、把握できていないところにコメが流れ、留まっているからなのではないか。備蓄米放出で、減った21万トン分のコメが市場に出れば、価格は落ち着くのではないか、というのが農水省の見立てです。
では一体、21万トンはどこに消えたのでしょうか。去年夏以来の、コメ不足やコメ高騰を受けて、農協などの集荷団体とは別に、農水省が把握していない様々な業者や個人が、コメを買い付けたと見られます。コメは保管できる作物です。価格が上がることがわかっている商品を早めに買って、利ざやを稼ぐのは商売の基本です。まだまだ価格が上がると思えば、なかなか売りません。
だとすれば、この人たちが、「これ以上持っていても損が出るので、売却しよう」という状況になるかどうかが、一番重要なポイントです。今、言われている1~2割の価格低下で、そうした状況になるかどうかは微妙だと、私には思えます。
滞っているのは「流通」で「コメは足りている」という農水省
農水省は、今回放出する備蓄米21万トンを、近い将来、市場から買い戻すとしています。「コメは足りており、滞っているのは流通だけ」というのが、農水省の論理だからです。しかし、買い戻しが条件であれば、再びコメ価格が上昇に転じるかもしれないと期待するのが、普通の心理です。この期待が、在庫維持につながり、価格低下を妨げる効果は、それなりに大きいのではないでしょうか。
さらに、本当にコメは足りているのか、これがそもそも疑問です。コメが足りているのであれば、当初、農水省が言っていた通り、どこかで価格は落ち着いたのではないのか、そもそも去年、あれほど店頭からコメがなくなることもなかったのではないか、と思えるのです。
もしコメが足りていないのであれば、端境期の今年の夏には、再びコメが不足し、価格は再度、高騰に転じる恐れもあるのではないでしょうか。
消費者不在の政策で一層のコメ離れ
一連の動きを振り返ってみると、農水省の見通しの甘さに加え、消費者不在の行政であることがよくわかります。農家所得の維持こそが最大の命題で、そのために「生産抑制」するという発想です。
減反政策は表面上やめたことになっていても、年間数千億円も転作奨励補助金を出しており、「生産抑制」は脈々と続いています。今回の騒動でコメ価格が上がり始めた当初、農水省は農家所得確保の観点から、好ましいとさえ思っていたのではないでしょうか。
インフレでパンや麺類も値上がりする中、唯一自給できるコメは、本当なら消費拡大のチャンスでした。その好機を逃したばかりか、コメ離れを自ら促した展開には呆れてしまいます。今回の「失政」と言っていい責任を、政治家も官僚も、誰もまだ取っていません。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
・スマホのバッテリーを長持ちさせるコツは?意外と知らない“スマホ充電の落とし穴”を専門家が解説【ひるおび】
・「パクされて自撮りを…」少年が初めて明かした「子どもキャンプの性被害」 審議進む日本版DBS “性暴力は許さない”姿勢や対策“見える化”し共有を【news23】
・【検証】「布団の上に毛布」が暖かい説 毛布は布団の「上」か「下」か 毛布の正しい使い方【Nスタ解説】

